こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
秋になって急に肌が乾燥してきたり、夏に受けた紫外線ダメージが気になり始めたりしていませんか?
保湿をしっかりしているのに肌の内側から乾いている感じがする…そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、秋の肌トラブルの根本原因は「水分代謝の乱れ」にあると言われているんです!
夏の紫外線ダメージと秋の乾燥が重なることで、肌のバリア機能が低下し、水分を保持する力が弱まってしまうんですね。
この記事では、体の内側から水分代謝を整えて、肌のバリア機能をサポートする具体的な方法をお伝えします✨
東洋医学の視点も交えながら、今日から実践できるセルフケアをご紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
この記事はこんな方におすすめです:
- 秋になると急に肌が乾燥する方
- 夏の紫外線ダメージが気になっている方
- 化粧水が浸透しにくいと感じている方
- 朝はむくみ、夕方は乾燥する方
- 体の内側から肌質を変えたい方
この記事を読むとわかること:
- 秋の肌トラブルと水分代謝の関係
- 水分代謝を整える3つのステップ
- 東洋医学的視点からの秋の肌ケア
- 今日から始められる具体的なセルフケア方法
柏市で唯一【Beiku美容鍼】を受けたい方はこちら
美容を本気で内側から考える当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、10年後もきれいでいるための体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし美容を体の内側から根本的にサポートすることに興味がおありでしたら、一度ご相談ください。
秋の肌が乾燥する本当の理由とは?
夏の紫外線ダメージが秋に現れるメカニズム
「夏はしっかりUVケアしていたのに、秋になってシミが濃くなった気がする…」
そんな経験はありませんか?
実は、紫外線によるダメージは、受けた直後ではなく約3ヶ月後に肌表面に現れると一般的に言われているんです。
紫外線を浴びると、肌の中で活性酸素が発生します。
この活性酸素が肌細胞を傷つけることで、メラニンの過剰生成やコラーゲンの損傷が起こると考えられているんですね。
さらに、紫外線は肌のバリア機能を構成する角質層にもダメージを与えます。
角質層が傷つくと、肌の水分を保持する力が弱まり、秋の乾燥した空気にさらされることで、より一層乾燥が進んでしまうんです💦
ターンオーバー(肌の新陳代謝)の周期も乱れやすくなり、古い角質が溜まって、くすみやゴワつきの原因にもなると言われています。
秋の気候変化が水分代謝に与える影響
秋は気温も湿度も急激に変化する季節です。
湿度は夏の70〜80%から、秋には50〜60%程度まで低下すると言われています。
この湿度の低下が、肌の乾燥を加速させる大きな要因なんですね。
また、朝晩の気温差が大きくなることで、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経は体温調節や水分代謝にも深く関わっているため、そのバランスが崩れると、体内の水分循環がうまくいかなくなると考えられているんです。
夏に比べて発汗量も減るため、体内の老廃物が排出されにくくなり、むくみやすくなるという側面もあります。
「朝は顔がむくんでいるのに、夕方には肌がカサカサ」という状態は、まさに水分代謝の乱れのサインなんですよ。
肌のバリア機能低下のサイン
肌のバリア機能が低下すると、こんなサインが現れます。
- 化粧水が浸透しにくい、肌の表面で弾かれる感じがする
- 洗顔後に肌がつっぱる、ピリピリする
- ファンデーションが粉を吹く、うまくなじまない
- 赤みやかゆみが出やすくなった
- 朝のむくみと夕方の乾燥が同時に起こる
これらのサインは、肌が本来持っている水分保持力が弱まっている証拠なんです。
表面的な保湿ケアだけでは追いつかない状態になっているかもしれません。
だからこそ、体の内側から水分代謝を整えることが大切なんですね✨
季節の変わり目の肌トラブルについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
体質を全体からとらえた水分代謝の背景
東洋医学でみる秋と「肺」の関係
東洋医学では、秋は「肺」の季節とされています。
五行説という考え方では、秋は「金」の性質を持ち、この「金」に対応する臓器が「肺」なんです。
肺は呼吸器系としての役割だけでなく、皮膚や水分代謝とも深く関わっていると伝統的に考えられてきました。
「肺は皮毛を主る」という言葉があり、肺の機能が皮膚の潤いや毛穴の開閉に影響を与えるとされているんですね。
また、「肺は水の上源」とも言われ、体内の水分を全身に巡らせる出発点としての役割があると考えられています。
秋になると空気が乾燥し、肺がその影響を受けやすくなるため、肺の機能が低下すると、皮膚の乾燥や水分代謝の乱れにつながるというわけです。
水分代謝に関わる「脾・肺・腎」の働き
東洋医学では、水分代謝は一つの臓器だけでなく、複数の臓器が連携して行っていると考えられています。
特に重要なのが「脾・肺・腎」の三つの臓器なんです。
脾(消化器系)の役割:
食べ物や飲み物から水分を吸収し、全身に運ぶ働きをサポートすると言われています。
脾の機能が弱ると、水分がうまく運ばれず、むくみや消化不良の原因になると考えられているんですね。
肺の役割:
吸収された水分を全身に分配し、特に皮膚への供給に関わるとされています。
肺の機能が低下すると、皮膚が乾燥しやすくなると言われているんです。
腎の役割:
水分の排泄と再吸収のバランスを調整すると考えられています。
腎の機能が弱ると、むくみや冷えの原因になるとされているんですね。
この三つの臓器がバランスよく働くことで、体内の水分代謝が正常に保たれると東洋医学では考えられています。
気・血・水のバランスから見た秋の肌トラブル
東洋医学には「気・血・水」という考え方があります。
これは体を構成する三つの要素で、このバランスが崩れると様々な不調が現れると言われているんです。
気虚(ききょ):
エネルギー不足の状態で、水分を全身に巡らせる力が弱くなっていると考えられます。
疲れやすい、だるいといった症状とともに、むくみや肌のハリ不足が現れやすいとされています。
血虚(けっきょ):
栄養や潤いを運ぶ血が不足している状態です。
肌の乾燥、髪のパサつき、爪が割れやすいなどの症状が出やすいと言われています。
水滞(すいたい):
余分な水分が体内に溜まってむくみを起こしている状態です。
朝の顔や手足のむくみ、体の重だるさなどが特徴とされています。
秋は「気虚」と「水滞」が同時に起こりやすい季節と言われているんです。
エネルギー不足で水分を巡らせる力が弱まり、その結果、水分が停滞してむくみが起こる…そんな悪循環が生まれやすいんですね💦
体質に合わせた肌のケアについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
水分代謝を整えて肌バリアをサポートする3つのステップ
【朝】白湯習慣で内臓から温める
朝一番の白湯習慣が、水分代謝をサポートする第一歩です✨
なぜ白湯が水分代謝をサポートするのか
夜間、私たちの体温は少し下がります。
朝、温かい白湯を飲むことで、内臓温度を上げることができると言われているんです。
内臓が温まると、消化器系の働きがサポートされ、東洋医学でいう「脾」の機能を助けると考えられています。
冷たい水を飲むと、逆に内臓を冷やしてしまい、水分代謝が低下する可能性があるんですね。
白湯の作り方と飲み方のコツ
- 水を一度しっかり沸騰させる
- 50〜60度まで冷ます(熱すぎず、ぬるすぎない温度)
- 起床後30分以内に飲む
- ゆっくり10分かけて飲む
- コップ1杯(150〜200ml)が目安
一気に飲むのではなく、少しずつ味わうように飲むのがポイントです。
体の中からじんわり温まる感覚を味わってみてくださいね。
期待される変化(個人差があります)
- 朝の顔のむくみが気にならなくなる
- お通じのリズムが整いやすくなる
- 体が内側から温まる感覚
- 肌の調子が安定してくる
実際、スタジオシュカに通われている方の中にも、白湯習慣を始めてから「朝のむくみが減った」「化粧ノリが良くなった」というお声をいただくことが多いんですよ😊
【昼】食事のタイミングと内容で水分代謝をサポート
何を食べるかだけでなく、「いつ食べるか」も水分代謝には大切なんです!
水分代謝をサポートする食材
東洋医学では、食材にもそれぞれ性質があると考えられています。
- 小豆・黒豆:利尿作用が期待され、余分な水分の排出をサポートすると言われています
- 冬瓜・きゅうり:体の余分な水分を排出する働きがあるとされています(ただし冷やす性質があるので、温めて食べるのがおすすめ)
- 山芋・長芋:脾の機能をサポートし、水分の吸収と運搬を助けると考えられています
- 発酵食品:腸内環境を整えることで、全身の巡りをサポートすると言われています
避けたい食習慣
- 冷たい飲み物の過剰摂取(内臓を冷やす)
- 生野菜ばかりの食事(体を冷やしやすい)
- 塩分の取りすぎ(むくみの原因)
- 食事時間の不規則化(体内リズムが乱れる)
食事のタイミング
体内時計に合わせた食事のタイミングも重要です。
- 朝食:7〜8時(体内時計をリセット)
- 昼食:12〜13時(消化機能が最も高まる時間帯と言われています)
- 夕食:18〜19時(就寝3時間前までに)
毎日同じ時間に食事をすることで、体内リズムが整い、水分代謝もスムーズになると考えられているんです。
食事のタイミングについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧くださいね。
【夜】入浴と睡眠で肌再生をサポート
夜の過ごし方が、翌朝の肌の状態を大きく左右します✨
水分代謝をサポートする入浴法
- 38〜40度のぬるめのお湯に設定する
- 15〜20分の半身浴または全身浴
- 入浴後は常温の水をコップ1杯飲んで水分補給
- 就寝2時間前までに入浴を済ませる
熱すぎるお湯は交感神経を刺激して、睡眠の質を下げる可能性があります。
ぬるめのお湯でゆっくり温まることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できると言われているんです。
入浴によって体温が上がり、その後ゆっくり下がっていくタイミングで眠りにつくと、質の良い睡眠をサポートすると考えられています。
睡眠中の肌再生をサポートする環境づくり
- 寝室の湿度を50〜60%に保つ(加湿器の活用)
- 室温は16〜19度が理想的とされています
- 22時〜2時のゴールデンタイムを含む7時間睡眠を確保
- 就寝前1時間はスマホやパソコンの使用を控える
睡眠中は成長ホルモンが分泌され、肌の修復や再生が行われると言われています。
特に入眠後の最初の3時間が重要とされているんですね。
この時間帯に深い眠りに入れるかどうかが、肌の調子を左右すると考えられています。
睡眠と美肌の関係については、こちらの記事でも詳しくお伝えしていますので、参考にしてみてくださいね。
柏市で唯一【Beiku美容鍼】を受けたい方はこちら
美容を本気で内側から考える当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、10年後もきれいでいるための体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし美容を体の内側から根本的にサポートすることに興味がおありでしたら、一度ご相談ください。
今日から始められるセルフケア実践法
水分代謝をサポートするツボ押し
東洋医学では、ツボ(経穴)を刺激することで、体の巡りをサポートすると考えられています。
水分代謝に関わるツボを3つご紹介しますね✨
三陰交(さんいんこう)
- 位置:内くるぶしから指4本分上のところ
- 効果:脾・肝・腎の三つの経絡が交わるツボとして、水分代謝全般をサポートすると伝統的に言われています
- 押し方:親指で優しく30秒、左右各2回ずつ
女性特有の悩みにも用いられることが多いツボなんですよ。
陰陵泉(いんりょうせん)
- 位置:膝の内側、すねの骨の際のくぼんだところ
- 効果:脾経の重要なツボで、むくみケアに用いられると言われています
- 押し方:親指でやや強めに20秒、左右各2回ずつ
押すと少し痛みを感じる方もいますが、それは水分が滞っているサインかもしれません。
太白(たいはく)
- 位置:足の親指の付け根、内側のくぼんだところ
- 効果:脾の原穴として消化機能をサポートすると考えられています
- 押し方:親指で円を描くように30秒
朝晩のツボ押しを習慣にすることで、体の巡りをサポートすることが期待できます(個人差があります)。
むくみケアについては、こちらの記事でも詳しく解説していますよ。
肺の機能をサポートする呼吸法
深い呼吸は、肺の機能をサポートするだけでなく、自律神経のバランスを整える効果も期待できると言われています。
腹式呼吸の実践方法
- 背筋を伸ばして座る(椅子でも床でもOK)
- 鼻からゆっくり4秒かけて息を吸う(お腹を膨らませるイメージ)
- 2秒息を止める
- 口からゆっくり8秒かけて息を吐く(お腹をへこませる)
- これを5〜10回繰り返す
朝晩5分ずつ実践するのがおすすめです。
吐く息を吸う息の2倍の長さにすることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できると言われているんです。
期待される効果(個人差があります)
- 自律神経のバランスをサポート
- 肺の機能を高めると言われている
- リラックス効果が期待される
- 睡眠の質の向上が期待できる
自律神経と肌の関係については、こちらの記事でも詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧くださいね。
全身の巡りをサポートする軽い運動
激しい運動は必要ありません。軽い運動で十分なんです!
ウォーキング
- 1日20分、朝または夕方に行う
- 早歩きで心拍数を少し上げる
- 腕を大きく振って全身を使う
- 呼吸を意識しながら歩く
ウォーキングは全身の血流を促し、リンパの流れもサポートすると言われています。
朝に行えば体内時計もリセットされ、夕方に行えば夜の睡眠の質向上も期待できるんですよ。
ストレッチ
- 股関節周り:あぐらの姿勢で前屈、股関節をほぐす(下半身の巡りサポート)
- 肩甲骨周り:両手を後ろで組んで上下に動かす(上半身の巡りサポート)
- 足首回し:座った状態で足首を大きく回す(末端の巡りサポート)
お風呂上がりの体が温まった状態で行うと、より効果的と言われています。
無理のない範囲で、毎日続けることが大切ですよ✨
鍼灸でサポートできること
体質に合わせた経絡とツボへのアプローチ
セルフケアも大切ですが、専門家による施術で、より深い部分からのアプローチも期待できます。
鍼灸では、お一人おひとりの体質を東洋医学的に見立てることから始まります。
「気虚」「血虚」「水滞」など、その方の体質タイプを判断し、それに合った経絡とツボを選択していくんです。
例えば、水分代謝が滞っている方には、脾経・肺経・腎経といった経絡にアプローチすることで、体全体のバランスを整えることを目指します。
セルフケアでは届かない深部へのアプローチが期待されるのが、専門施術の特徴なんですね。
スタジオシュカの水分代謝改善サポート
スタジオシュカでは、美容を本気で内側から考えたサポートを提供しています。
カウンセリング重視
まずは、じっくりとお話を伺います。
- 現在の生活習慣(食事・睡眠・運動・ストレス)
- お肌の悩み(乾燥・むくみ・くすみなど)
- 体調全般(冷え・疲労・便秘など)
東洋医学的な体質診断(舌診・脈診・腹診)も行い、あなたの体質を総合的に判断します。
施術内容
- 水分代謝に関わる経絡(脾経・肺経・腎経)へのアプローチ
- 顔だけでなく全身のツボを使った施術
- 自律神経のバランスをサポートする鍼灸
- お一人おひとりに合わせたオーダーメイド施術
生活習慣のサポート
施術だけでなく、日常生活でできることもお伝えします。
- 食事、睡眠、運動など具体的なアドバイス
- セルフケアの方法を丁寧に指導
- 定期的な体質チェックとケアの見直し
10年後もきれいでいるための体づくりを、一緒にサポートさせていただきます✨
セルフケアと専門施術の違い
セルフケアと専門施術、それぞれに役割があります。
セルフケアの役割:
- 毎日のベースとして体質を整える
- 生活習慣の中で継続的に行える
- 自分の体の変化に気づきやすくなる
専門施術の役割:
- 体質の根本からアプローチすることを目指す
- セルフケアでは届かない深部へのアプローチ
- 専門家の視点からの体質判断とアドバイス
両方を組み合わせることで、より良い結果が期待されます(個人差があります)。
まずはセルフケアから始めて、「もっと本格的に体質改善したい」と思われたら、ぜひスタジオシュカにご相談くださいね。
紫外線ダメージのケアについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
まとめ:秋こそ体の内側から肌をケアしましょう
秋の肌トラブルは、夏の紫外線ダメージと秋の乾燥という二重のストレスが原因です。
そして、その根本には「水分代謝の乱れ」があると言われているんですね。
表面的な保湿ケアだけでなく、体の内側から水分代謝を整えることが、肌のバリア機能をサポートする鍵になります✨
今日からできる3つのステップを、ぜひ実践してみてください!
- 朝の白湯習慣で内臓から温める
- 食事のタイミングと内容を見直す
- 夜の入浴と睡眠環境を整える
小さなことからコツコツと。それが、10年後のあなたの肌を作ります。
東洋医学では、秋は「収斂(しゅうれん)」の季節とされています。
夏に発散したエネルギーを内側に蓄える時期なんですね。
だからこそ、体の内側を整えることに最適な季節なんですよ。
そして、セルフケアだけでは難しいと感じたら、東洋医学の専門家に相談するのも一つの方法です。
スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせた水分代謝改善のサポートをさせていただいています。
鏡を見るのが楽しくなる…そんな毎日を一緒に作っていきましょうね!
あなたの肌と体が、本来の美しさを取り戻すお手伝いができれば嬉しいです💕
柏市で唯一【Beiku美容鍼】を受けたい方はこちら
美容を本気で内側から考える当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、10年後もきれいでいるための体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし美容を体の内側から根本的にサポートすることに興味がおありでしたら、一度ご相談ください。
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。当院の施術は医療行為の代替ではありません。体調に不安がある場合は、まず医療機関にご相談ください。

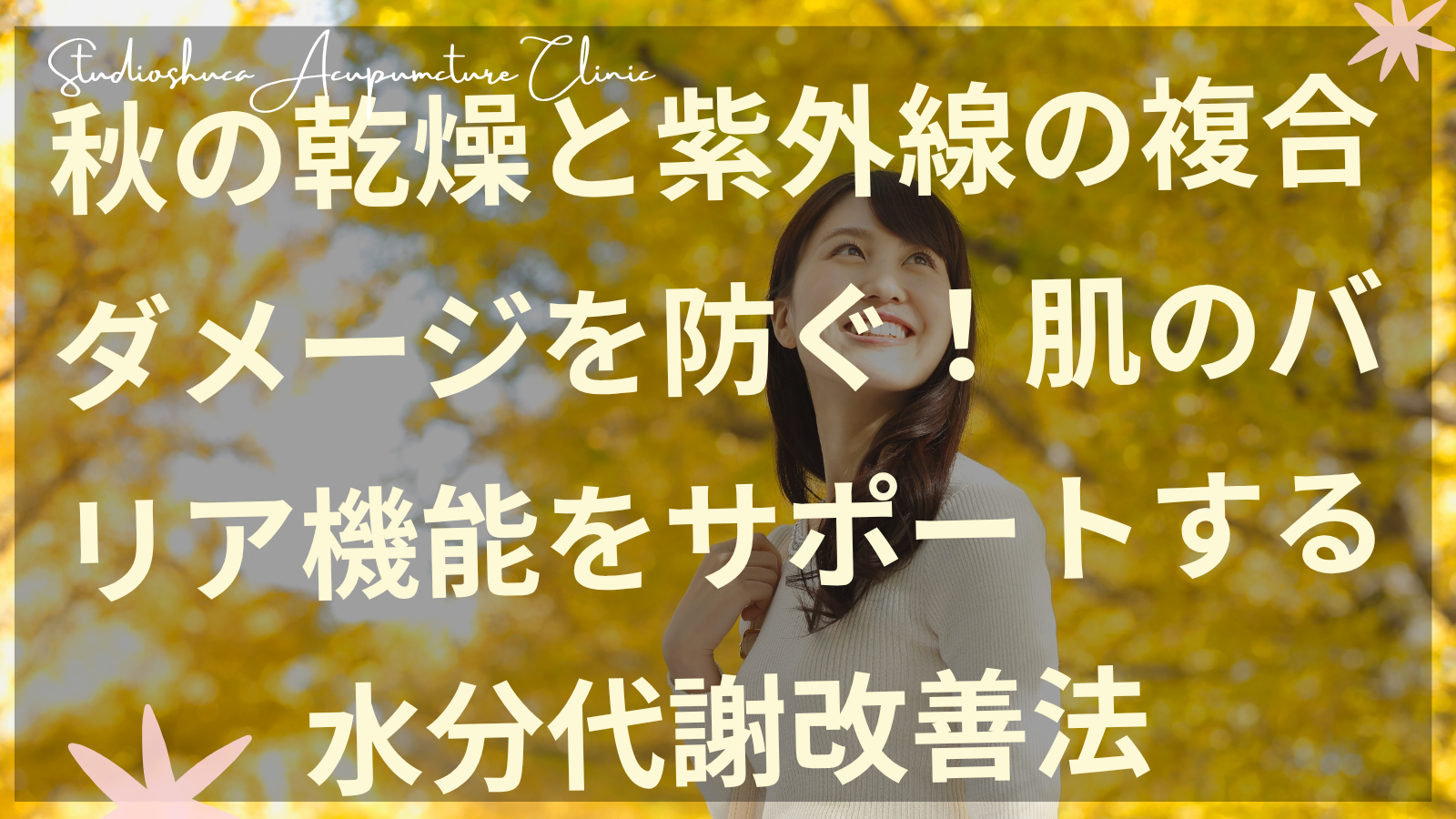
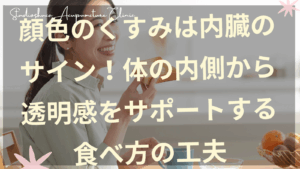
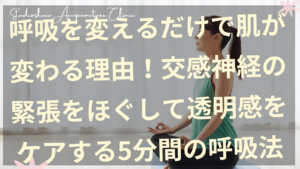
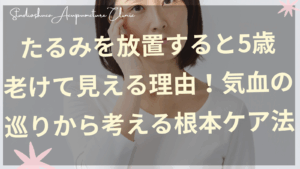
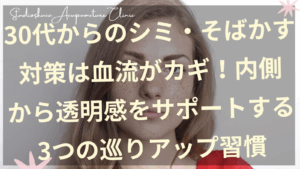
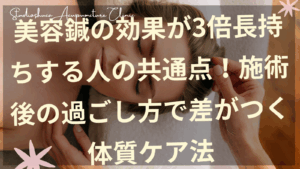
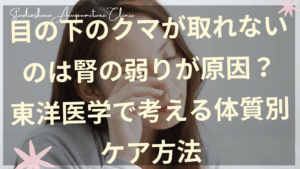
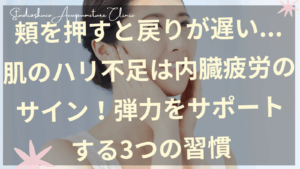
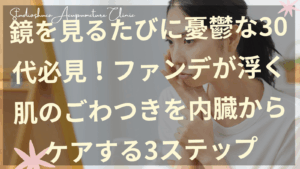
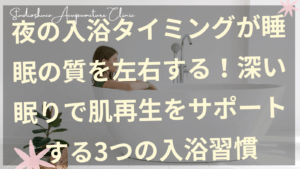
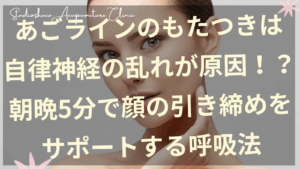
コメント